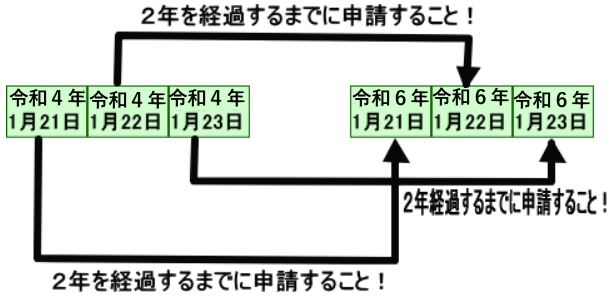在職中の傷病手当金手続き
☆在職中の傷病手当金
在職中の傷病手当金=会社が申請書を提出
通常は1ヶ月ごとに申請
- 傷病手当金の時効は傷病手当金の権利が発生した日ごとに、その翌日から2年です。
- 例えば、令和4年 1月18日に何らかの傷病で病院に入院し、その結果、翌月17日まで(2月17日まで1ヶ月間入院したとします。
最初の3日間(1月18日~1月20日)は待期期間ですので、傷病手当金は受給できませんが、その後の1月21日~2月17日までの期間につきましては、それぞれの日について2年経過するまでに傷病手当金を申請しないと、傷病手当金はもらえません。
- つまり、令和4年1月21日の傷病手当金は令和6年1月21日(民法の原則;翌日起算により)までに請求しないともらえないことになります。
- 同様に、令和4年1月22日の傷病手当金は令和6年1月22日までに請求しないともらえないことになります。
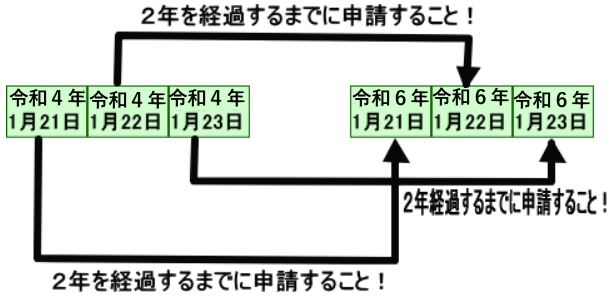
申請してから、約1ヵ月後に口座に振り込まれます。
- 「傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)」を提出してから、従業員さんの口座にお金が振り込まれるまでには約1ヶ月かかります。
- 健康保険組合によっては約2ヶ月かかるケースが有ります(提出日の締日を設定している健康保険組合)。
1ヶ月ごとに申請するのが良いでしょう。
給与の締切日が経過したら申請しましょう。
- 1回目の申請時には、以下の書類が必要となります。
- 申請期間分の出勤簿(コピーで可)又はタイムカード(コピーで可)
- 申請期間前1ヶ月分の出勤簿(コピーで可)又はタイムカード(コピーで可)
- 申請期間分の賃金台帳(コピーで可)又は給与明細(コピーで可)
- 申請期間前1ヶ月分の賃金台帳(コピーで可)又は給与明細(コピーで可)の提出が必要な健康保険組合も有ります。
- 在職中は全国健康保険協会に加入していた場合、在職期間分の申請について 「出勤簿のコピー」・「賃金台帳のコピー」は添付不要です。
- 2回目以降の申請には、原則、出勤簿・賃金台帳等の添付書類はは不要ですが、2回目以降についても申請期間分の出勤簿(コピー)・賃金台帳(コピー)等の提出が必要となるケースが有ります。
- 在職中は全国健康保険協会に加入していた場合、在職期間分の申請について 「出勤簿のコピー」・「賃金台帳のコピー」は添付不要です。
- 給与の締切日が経過し、給与の額が確定したら(給料無支給で「0円」なら「0円」でOK)、以下の書類を持って、自分の加入している保険者(全国健康保険協会又は健康保険組合)に行きましょう。書類郵送については郵送でもOKです。
- 出勤簿(コピーで可)又はタイムカード(コピーで可)
- 賃金台帳(コピーで可)又は給与明細(コピーで可)
- 「傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)」
- 「第三者行為による傷病届」⇒第1回目申請時のみ提出
- 第三者の不注意等によって病気・怪我を発症してしまった場合(例:交通事故、ケンカ等)に必要
会社の担当者様は従業員さんに申請書をあげましょう。
- 「傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)」には「療養担当者が意見を書くところ」という欄があります。要するに、医師に「労務不能」の証明をしてもらうわけです。ですから、従業員さんは会社の担当者から「傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)」をもらって、病院に行かねばなりません。協会けんぽの場合は、協会けんぽのサイトから印刷できます。健康保険組合のサイトから印刷できる健康保険組合も有ります。
- 「傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)」の「療養担当者が意見を書くところ」の欄には医師により記入してもらいます。
- 要するに、傷病手当金の申請には医師の「診断書」は不要です。その代わり、医師により「傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)」の「療養担当者が意見を書くところ」に記入をしてもらって、「労務不能」の証明をしてもらうわけです。
家族手当・役職手当等の手当が出る場合の注意
- 1ヶ月の期間中に、例えば3日間しか出勤しなかったのに、役職手当が丸々満額支給された場合には、原則、その額を30日で割った額が単価となり、傷病手当金1日分の額から控除されます。
- ※上記の1ヶ月の期間中とは、会社の締〆の期間です。例:20日〆の会社の場合には、「3月21日~4月20日=1ヶ月の期間」
☆傷病手当金の時効
労務不能の日ごとにその翌日から2年
- 傷病手当金の時効は傷病手当金の権利が発生した日ごとに、その翌日から2年です。
- 例えば、「令和4年1月25日分の傷病手当金」については、「令和6年1月25日」が時効であり、「令和6年1月26日」以降に申請することはできなくなります。
時効にかからなければ、退職後に在職中の分を請求してもOK
- 退職後に申請しても、傷病手当金の権利発生日~2年経っていなければ、傷病手当金の申請は可能です。
- ただ、あまり前の期間の「労務不能証明」を医師に頼んだ場合、医師に断られるケースがあります。なるべく早めに申請しましょう。
- 一旦退職してしまうと、以前勤めていた会社とは疎遠になってしまうのが通例ですので、手続きを頼み辛くなるケースが多いと思います。ですから、なるべく早く申請しましょう。
- 退職後にする最初の傷病手当金申請については、在職期間分が含まれているので、会社を通さねばなりません。さらに、健康保険組合の場合は、①出勤簿又はタイムカード(いずれもコピーで可)と②賃金台帳又は給与明細(いずれもコピーで可)も必要となります。