貰うための条件
☆傷病手当金をもらうための条件
疾病又は負傷のために療養中であること
- 疾病又は負傷の為に療養中であること(医師の指示による自宅療養を含む)。
疾病又は負傷のために労働不能であること。
- 労務に服することができないこと。=仕事ができないこと。
- 傷病手当金支給申請書に医師の証明欄がありますので、その欄に記入してもらいます。
- 医師の許可等をもらって、出勤した場合には、傷病手当金はもらえません。医師が労働可能と判断した場合には、傷病手当金はもらえません。
疾病又は負傷のために労働できない日が3日連続あること。
3日間の待期期間後の療養期間については報酬が出ないこと。但し、退職後の傷病手当金を受給する場合は、退職日まで給与全額支払われてもOK
- 3日連続して労務に服することができなくなった場合に4日目からもらえます。
※3日間には日曜・祝祭日・有給休暇も含まれます。
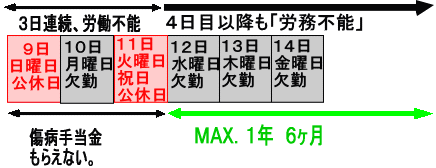
※また、3日間連続有給休暇をとっていてもOKですし、3日間連続して報酬をもらっていてもOKです。
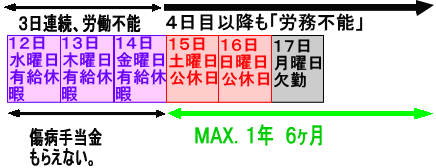
※待期期間3日については連続していなければなりません。
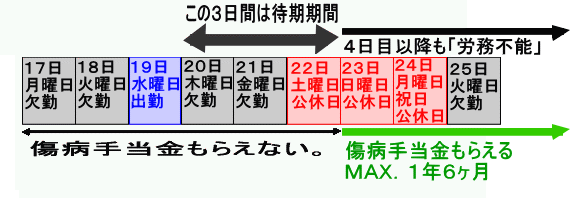
- 3日間の待期後の期間については、報酬(給料)が出ないこと。報酬が出ても傷病手当金の額より少ない場合にはその差額が(「傷病手当金-報酬」)、傷病手当金としてもらえます。
- 3日間の待期期間後の期間について「労務不能」であり、その3日間は欠勤したが通常の給与額が支払われた場合(有給休暇等の場合)には、傷病手当金そのものは支給されませんが、傷病手当金の受給権(傷病手当金をもらう権利)を取得することはできます。
- 「待期期間」が正しいです。「待機期間」は誤りです。
- 公休日についても、原則、もらえます。⇒公休日=会社が予め指定した休日
- 事業所の休日(会社が休みの日=会社の盆休み・正月休み等)・土曜・日曜・祝祭日等であっても、上記の条件を満たしていれば、もらえます。要するに、会社の所定休日であっても、医師が労務不能と判断し、給料が出なかったり、若しくは、給料が出た場合でも、傷病手当金の額より少なければ、傷病手当金はもらえます。要するに、暦日単位で貰えます。
- ただし、下記のケースでは傷病手当金は不支給(支給停止)となります。
例:給与の締日が月末。令和5年8月1日から令和5年8月31日までは、「有給休暇+公休日」により一切出勤しなかった。

- もし退職日が令和5年8月31日の場合、最低限、在職最後の4日間(令和5年8月28日から令和3年8月31日まで)は申請しなければ退職後の傷病手当金(正式には「資格喪失後の継続給付」と言います)はもらえません。⇒「令和5年8月1日から令和5年8月31日まで」は、傷病手当金がもらえないとわかっていても。
「退職後の傷病手当金(一般被保険者資格喪失後の傷病手当金)」の受給権を獲得するためには「最低限在職最後の4日間(最低限一般被保険者最後の4日間)」を申請します。
- 給料と傷病手当金との調整についてはこちらをクリック
- 退職後の傷病手当金(正式には健康保険法第104条に規定する「資格喪失後の継続給付」)について
退職後の傷病手当金を受給する場合、退職日まで有給休暇であり、退職日まで給与が全額支払われている場合は、在職期間分は傷病手当金はもらえません。ただし、在職最後の期間の傷病手当金を申請することにより、傷病手当金の受給権(傷病手当金をもらう権利)を獲得できるので、在職最後期間の傷病手当金は申請する必要が有ります(在職最後期間については傷病手当金がもらえないと、わかっていても)。
退職後も傷病手当金を貰う人は退職日まで連続1年以上の一般被保険者期間が必要 )。
退職日の翌日以降について下記の条件をクリアーすれば傷病手当金は受給可能です。
❶退職日までに、健康保険の一般被保険者期間(いわゆる「社会保険」の期間)が連続1年以上有ること。保険者(≒会社)が異なっていても、退職日までに連続1年以上の健康保険一般被保険者期間が有ればOKです。
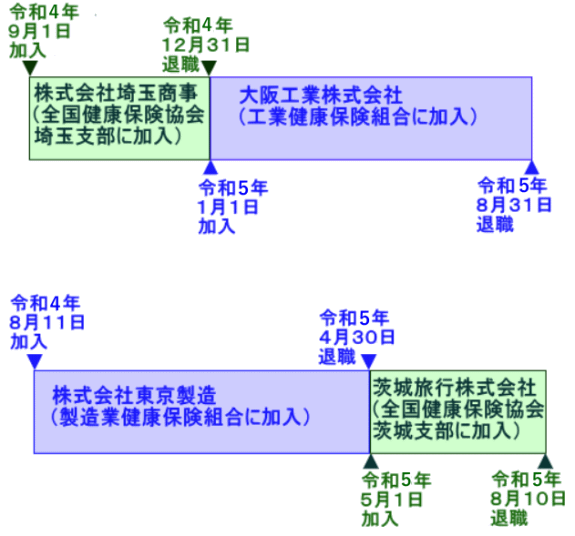
- 下のケースでは、退職後(一般被保険者資格喪失後)の傷病手当金は、もらえません。
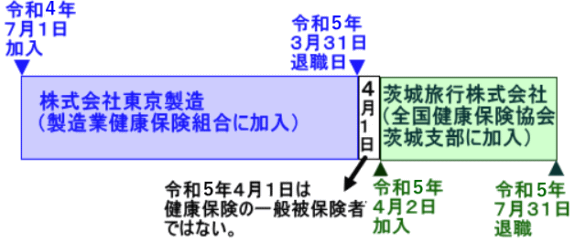
❷退職日の前日までに「連続3日以上の労務不能期間」が有ること。
例えば、退職日が令和5年8月31日の場合、「令和5年8月28日から令和5年8月30日まで」が労務不能であることが条件です。「労務不能」というのは、労働不能ということです。即ち、欠勤・有給休暇・公休日等により会社へ出勤せず、且つ医師が傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)の医師記入欄に記入してくれること」 ※医師に記入してもらうのは「労務不能期間(申請期間)」が経過した後です。
退職後の傷病手当金がもらえない例を記します。
退職日が令和5年8月31日で、「令和5年8月27日まで」は通常勤務。「令和5年8月28日から令和5年8月31日まで」の3日間について、「8月28日(有給休暇)+8月29日(出勤)+8月30日(欠勤)」のケースです。即ち、会社へ出勤すると、「労務可能=労働可能」となります。退職日直前の期間については、有給休暇・公休日・欠勤無給等をとるようにして下さい。
いずれにしましても、退職直前の期間には十分注意しましょう。
❸退職日が「労務不能」であること。
退職日が令和5年8月31日の場合は、令和5年8月31日が「労務不能」であること。「労務不能」というのは、欠勤・公休日・有給休暇等により会社へ出勤せず且つ医師が傷病手当金の「医師記入欄」に記入してくれることです。※医師に記入してもらうのは「労務不能期間(申請期間)」が経過した後です。
❷と❸を一括して判断すると、令和5年8月31日が退職日の場合、「令和5年8月28日から令和5年8月31日まで」の4日間について、「欠勤・公休日・有給休暇」により会社へ出勤せず且つ医師が傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)の「医師記入欄」に記入してくれることが条件です。※医師に記入してもらうのは「労務不能期間(申請期間)」が経過した後です。
❹初診日が退職日以前4日以上前にあること。
医師は初診日以降の期間しか、傷病手当金支給申請書の医師記入欄に記入してくれません。例えば、初診日が令和5年8月29日で、退職日が令和5年8月31日の場合、医師は「令和5年8月29日から令和5年8月31日まで」の3日間については傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)の「医師記入欄」に記入してくれます(令和5年8月29日から令和5年8月31日までが労務不能であると認めてくれれば)。しかし、3日間では傷病手当金の受給権(貰う権利)は獲得できません。3日間の「労務不能期間」では、待期期間をクリアーしただけで終了してしまいます。つまり、退職後の傷病手当金(一般被保険者資格喪失後の傷病手当金)をもらう為には、在職期間(一般被保険者期間)に最低4日の「労務不能期間」が必要です。
したがいまして、退職日が令和5年8月31日の場合、退職後の傷病手当金(一般被保険者資格喪失後の傷病手当金)をもらうためには、初診日のリミットは「令和5年8月28日」です。そして、「令和5年8月28日から令和5年8月31日まで」の在職4日間については、「欠勤又は公休日若しくは有給休暇」でなければなりません。よって、「8月28日(欠勤:初診日)、8月29日(公休日)、8月30日(有給休暇)、8月31日(有給休暇:退職日)」というパターンであれば、退職後の傷病手当金は受給できる可能性が出てきます。
ここで例です。退職日が令和5年8月31日。給与計算の締日が月末。初診日が令和5年8月28日。退職日が令和5年8月31日(この日が2回目の通院)。となった場合、「令和5年8月28日から令和5年8月31日まで:有給休暇・欠勤・公休日・有給休暇により、この4日間は仕事をしていない」の在職期間については、令和5年9月1日以降に傷病手当金の申請手続きを開始します(在職期間分の申請なので、会社を経由します)。
❺退職後の期間も「労務不能」であること。
退職後も傷病手当金をもらうためには、退職後の期間についても「労務不能=労働不能」であることが条件です。
例えば、退職日が令和5年8月31日として、令和5年9月10日にアルバイトをした場合、今回の「退職後の傷病手当金(一般被保険者資格喪失後の傷病手当金)」をもらえるのは「令和5年9月9日まで分」です。「アルバイトをした=労務可能」となるからです。
また、就職面接を受けた場合も、「労務可能」となります。例えば、退職日が令和5年8月31日で、就職面接を令和5年9月20日に受けた場合、今回の「退職後の傷病手当金(一般被保険者資格喪失後の傷病手当金)」をもらえるのは「令和5年9月19日まで分」です。「就職面接を受けた=労務可能」となるからです。
❻傷病手当金を受給した期間が通算して(合計して)1年6ヶ月未満であること。
❼3週間に1回(1日)は、通院(又は入院)して診療行為を受けること。
これは、健康保険法にも健康保険法の行政通達にも記されていません。しかし、診療していない期間が長くなると、医師が傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)の「医師記入欄」に記入してくれないことが有ります。したがいまして、3週間に1回(1日)は通院(又は入院)して、医師による診療行為を受けてください。できれば、2週間に1回通院(又は入院)することが理想です。
中には、「1週間に1回は通院してくれないと、私は傷病手当金支給申請書の医師記入欄に記入しません」と主張する医師も居るようです。
家族の被扶養者だけの期間しかない人は、傷病手当金は貰えません。
- 退職日まで健康保険の一般被保険者であり(健康保険一般被保険者期間が退職日まで連続1年以上有る場合)で、下記の場合は、家族の被扶養者となりながら、退職後の傷病手当金を受給できる可能性が有ります。
ただし、一般被保険者期間の標準報酬月額がかなり低い場合です(全国健康保険協会の場合は、標準報酬月額が160,000円以下の場合です=60歳未満の場合)。
具体的には以下の条件をクリアーする場合です。
❶「傷病手当金受給開始日の属する月以前12か月間の標準報酬月額の平均額」÷30×2/3<3,612円(60歳未満の場合」
※60歳未満の場合は、傷病手当金1日分の額が3,612円未満であることが条件です。
※退職日まで(資格喪失日の前日まで)に加入していた保険者(健康保険組合・全国健康保険協会等)での健康保険一般被保険者期間が12か月未満の場合は、下の2つのうち低い方の額を採用します。
❶傷病手当金申請者本人が「退職日まで(資格喪失日の前日まで)に加入していた保険者(健康保険組合・全国健康保険協会等)での傷病手当金申請者本人の健康保険一般被保険者期間の平均標準報酬月額
❷傷病手当金受給開始日の属する年度の前年度の9月30日に於けるその保険者内(傷病手当金申請者本人が加入していた健康保険組合・全国健康保険協会等)の被保険者の平均標準報酬月額
❷「傷病手当金受給開始日の属する月以前12か月間の標準報酬月額の平均額」÷30×2/3<5,000円(「60歳以上75歳未満」又は障害者の場合」)
※「60歳以上75歳未満」又は障害者の場合は、傷病手当金1日分の額が5,000円未満であることが条件です。
※退職日まで(資格喪失日の前日まで)に加入していた保険者(健康保険組合・全国健康保険協会等)での健康保険一般被保険者期間が12か月未満の場合は、下の2つのうち低い方の額を採用します。
❶傷病手当金申請者本人が「退職日まで(資格喪失日の前日まで)に加入していた保険者(健康保険組合・全国健康保険協会等)での傷病手当金申請者本人の健康保険一般被保険者期間の平均標準報酬月額
❷傷病手当金受給開始日の属する年度の前年度の9月30日に於けるその保険者内(傷病手当金申請者本人が加入していた健康保険組合・全国健康保険協会等)の被保険者の平均標準報酬月額
退職後の傷病手当金と任意継続被保険者制度は条件が異なります。
- 退職後の傷病手当金(一般被保険者資格喪失後の継続給付)は、任意継続被保険者には無い給付です。
- しかし、任意継続被保険者の条件をクリアーし、且つ、退職後の傷病手当金(一般被保険者資格喪失後の傷病手当金継続給付)の条件もクリアーした場合は、任意継続被保険者となりながら退職後の傷病手当金(一般被保険者資格喪失後の傷病手当金継続給付)を受給することは可能です。
- したがいまして、退職後の傷病手当金(一般被保険者資格喪失後の傷病手当金継続給付)の受給要件をクリアーした人が退職後の傷病手当金(一般被保険者資格喪失後の傷病手当金継続給付)を受給しながら、国民健康保険に加入するという選択肢もあります。
- しかし、任意継続被保険者の条件をクリアーし、且つ、退職後の傷病手当金(一般被保険者資格喪失後の傷病手当金継続給付)の条件もクリアーした場合は、任意継続被保険者となりながら退職後の傷病手当金(一般被保険者資格喪失後の傷病手当金継続給付)を受給することは可能です。
- 任意継続被保険者の期間に発生した傷病に対しては、傷病手当金は支給されません。
- しかし、退職後の傷病手当金(一般被保険者の資格喪失後の傷病手当金継続給付)は、任意継続被保険者となった後でも、続けることは可能です。
- 「退職後の傷病手当金(一般被保険者資格喪失後の傷病手当金継続給付)」と退職後の医療保険は別ものとして考えてください。つまり、任意継続被保険者になるための条件と退職後(一般被保険者資格喪失後)も傷病手当金をもらうための条件とは、まったく異なります。
- 任意継続被保険者となるためには、任意継続被保険者となるための条件をクリアーすればOKです。退職後の傷病手当金(一般被保険者資格喪失後の傷病手当金継続給付)をもらうためには、退職後の傷病手当金(一般被保険者資格喪失後の傷病手当金継続給付)を受給できるための条件をクリアーすればOKです。
- しかし、退職後の傷病手当金(一般被保険者の資格喪失後の傷病手当金継続給付)は、任意継続被保険者となった後でも、続けることは可能です。
「任意継続被保険者+傷病手当金」のケースが有ります。
「国民健康保険+傷病手当金」のケースも有ります。
- 会社を退職後、任意継続被保険者となった後でも傷病手当金を貰い続けることができるケースがあります。
- このケースというのは、お勤めしていた時代にもらっていた傷病手当金(お勤めしていた時代に発生した傷病と同一の傷病による傷病手当金)を、任意継続被保険者となった後も貰い続けるケースです。任意継続被保険者となった後に発生した傷病については、「退職後の傷病手当金(一般被保険者資格喪失後の傷病手当金)」は支給されません。要するに、「退職後も、病気や怪我で仕事を見つけることが困難であるから、お勤めしていた時代の給料1日分の約67%は出しますよ」という趣旨のお金です。
- 詳しくはこちらをクリック
- 会社を退職後、国民健康保険に加入した状態で「退職後の傷病手当金(一般被保険者資格喪失後の傷病手当金)を受給するという選択肢もあります。
- つまり、退職後の公的医療保険は、任意継続被保険者又は国民健康保険を選択し、退職後の傷病手当金(一般被保険者資格喪失後の傷病手当金継続給付)を受給します(健康保険法第104条に規定する「資格喪失後の継続給付」の条件をクリアーした場合)。
- 退職後は 「任意継続被保険者+国民年金(60歳になるまで):傷病手当金」または
「国民健康保険+国民年金(60歳になるまで):傷病手当金」というのが一般的なパターンです。

